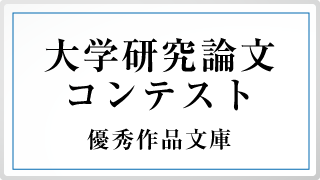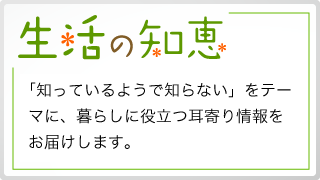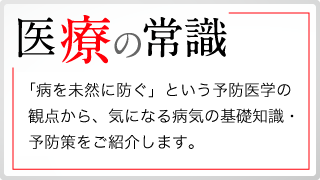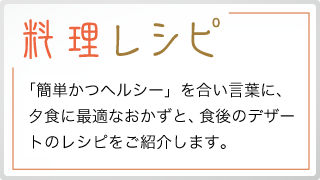国内のメガソーラーは、直流600Vのシステム電圧である設備が多く見受けられる。これは、電気事業法に基づく経済産業省の「電気設備に関する技術基準を定める省令」に準じているからだが、設備の建設・運営面での必須条件ではない。このため、日本国内でも1000Vのシステム電圧仕様にした設備を新設することは可能だ。一方、海外では1000Vのシステム電圧が主流となっている。1000Vソリューションを日本国内で初めて主力メニューとして前面に打ち出し、市場開拓を続けているのがABBだ。
●受け入れられつつある1000Vソリューション
ABB(本社:スイス・チューリヒ、日本本社:東京都渋谷区)は、重電関連機器や産業用ロボットなどを扱うグローバル企業だ。もちろん再生可能エネルギー関連機器も、事業の大きな柱となっている。
以前は、発電設備の主機としてGT24、GT26といったコンバインドサイクル発電プラント用のガスタービンなどを自社開発していたが、新規事業への参入もあり、送配電分野など技術的に優位な分野に特化する戦略を採ったため、現在は手掛けていない。日本国内のメーカーが1社ですべて提供できる体制を整えている姿勢とは趣が異なる面があるが、それでも送配電分野では世界のトップメーカーで、太陽光発電関連設備の場合パネル、ケーブル以外の周辺機器、関連機器はすべてラインナップにある。
太陽光発電設備の場合、パネルがラインナップにないため、実際の受注活動は入札を行うような超大型案件でパネルメーカーと組んで応札することもあり得るという。今までの受注実績では2MW未満の太陽光発電設備が多く、そういったものは単独の営業活動を重ねて獲得してきた。その営業活動で現在注力しているものの一つに、1000Vソリューションがある。
これは、国内で多く採用されている直流600Vのシステム電圧を1000Vにするものだ。現行の600Vに比べ送電ロスが64%まで削減できるほか、接続箱など周辺機器も削減できるため、約40%のメンテナンスコスト削減につながる。それにより、事業者の内部収益率が2~3%向上するという。現在はABBに追随する形で競合各社も1000Vを事業メニューに加え始めた。「600Vから1000Vに移行するトレンド自体は確実に起こっている」(阪本敏康・再生可能エネルギー事業推進部長)とのことだが、1000Vに注力し始めた頃はその効果に懐疑的な顧客もいたようだ。だが、徐々に導入事例が積み重なったほか、「1000V用ケーブルが(太陽光発電設備業界の中で)商品化されたり、規制緩和があってからは、1000Vが受け入れられていった。先行者が市場に居れば浸透は早い」(佐藤誠記・パワーエレクトロニクス・プロダクツ部セールスマネージャー)という事情も手伝い、今年3月末時点でのABBの受注案件では約8割が1000Vとなっている。後は、実績を積み重ねて市場にそのトレンドが浸透していけば、1000Vが市場で標準になっていくだろう。
しかし、まだ一部では、「工事の企業体でヘッドを務めるのは、たいていゼネコンか土木会社だ。企業の連合体で電気・計装関係は全て電設会社が請け負うが、電設会社で1000Vの設計施工を経験した社は少ない。そのソリューションが分からないから見積りで割高になることが多い。そこで1000Vはコストメリットがないと誤った認識を土木会社に与えてしまい、そこで一部足踏みが続いているような状況がある」(佐藤氏)などの点が依然普及のハードルにはなっているようだ。そこでABBでは、実際の建設時にその認識を正し、1000Vのメリットを広めていきたいとしている。そのために、2MW以下の案件を丹念に追いかけることが重要だという。この姿勢が、施工業者やエンドユーザーなどに評価され1000Vソリューションの浸透に弾みをつけたのだろう。
●先手を打ってきた機器開発とソリューション
1000Vソリューションと並び、現在最も注力しているのがパワーコンディショナー(PCS)だ。ABBは主に出力・容量の面で「国内では100kW以上からのPCSを揃えている」(阪本氏)という。基本的に、ABBは大容量大出力の非住宅用が専門で、グローバル事業では一部住宅用向けも手掛けてはいるものの、国内で住宅向けの機器販売は行っていない。

PCSでは5月、大容量太陽光発電向けの「PVS800」シリーズ(右写真)で875kW、1000kW用の機種を国内市場に投入した。この両機種は単機容量では国内最大級の機種で、最大効率98.8%、部分負荷効率98.6%を達成している。ABBの受注で主力を占める出力2MW以下の設備でも、複雑なシステム構成の単純化に寄与する。PVS800は100~1000kWまでの7機種があり、従来品比で電力密度が45%改善し、流通しているPCSではkW当たりの容積・占有面積が最も小さい。このPVS800シリーズは、2009年からアジア諸国などワールドワイドで250MW以上の出荷実績(2009~2011年)を持つ。国内大手メーカーのものでも、ここまで大容量のものは見当たらない。
 また、集電用接続箱「PVmax」(左写真)シリーズも筐体に樹脂を採用し、内部機構の発熱対策も施したことでコストパフォーマンスを高めている。日本国内の再生可能エネルギー市場が、欧州などと比べ数年は遅れている点を差し引いても、新鮮な印象を与える製品ばかりだ。これは、「一歩ずつ先のソリューションを開発して提供するということを心がけており、お客さまにも確かなソリューションを提供してきたという自負はある」(高橋宏行・低電圧機器事業部マーケティング部長)という姿勢が開発を後押ししてきたのだろう。
また、集電用接続箱「PVmax」(左写真)シリーズも筐体に樹脂を採用し、内部機構の発熱対策も施したことでコストパフォーマンスを高めている。日本国内の再生可能エネルギー市場が、欧州などと比べ数年は遅れている点を差し引いても、新鮮な印象を与える製品ばかりだ。これは、「一歩ずつ先のソリューションを開発して提供するということを心がけており、お客さまにも確かなソリューションを提供してきたという自負はある」(高橋宏行・低電圧機器事業部マーケティング部長)という姿勢が開発を後押ししてきたのだろう。
●国内市場10%超のシェアを目指す
そのほかの取り組みとしては、「まずは1つ1つの案件をトラブルなく施工することが重要だ。後は代理店など、多様な販売チャンネルを持つことだ。弊社も機器の販売だけでなく、施工に近い分野に足を踏み入れ、設備オーナーに近づくことも重要だと考えている」(阪本氏)という。グローバルでは欧州で既に1GWの施工実績もある。ただ現状では、国内でこれが主力事業にはならず、あくまでもコア事業は機器の受注・販売のため、その付帯的なサービスとして行われるようだ。
平成24年度の受注実績は、インストールベースでは40か所で約50MWの立ち上げが見られた。最新の受注実績はトータルで約80MWだという。「具体的なMW数は市場動向により変化するので具体的な数字は申し上げにくいが、産業用太陽光発電のPCSで、最低10%のシェアを目指している」(阪本氏)という。
では、ABBは中長期的な太陽光発電の市場環境をどう捉えているのか。
現在、企業の遊休地対策や地方自治体の非常用電源整備、財源確保策などとしてブーム化している太陽光発電設備の導入だが、電力会社の姿勢が問題視されるようになってきている。送電線に空きがない、新規発電事業者と系統連係の調整に非常に時間がかかる、更には北海道電力のように受け入れが限界…など、ブームの弊害とも考えられる現象が散見されている。そうすると、今後の新規案件が踊り場に差し掛かるのではと思えてくるが、ABBは現在のそういったネガティヴな面も含む市場環境をどう見ているのだろうか。
「数十MWクラスの大型案件は、現在具体化しているものがすべてで、今後立ちあがってくる可能性は少ない。北海道電力のような問題は、他の電力会社でも所轄管内の地域で太陽光発電が増えれば、当然直面する問題だ。ただ、難しくなってくるとそこを乗り越えようとする技術開発などが行われる。蓄電池とシステム化するのもその表れだし、FIT制度下のメガソーラーといっても、地産地消に近いような発電形態へのシフトが起こることはあり得る。こういう形で市場が続いていくのではないか」(阪本氏)と、特に心配はしていないようだ。
すると、再生可能エネルギーが「新エネルギー」の枠から徐々に商業電力のように定着した場合、今度は現在の買い取り価格が問題視されることが考えられる。商業電力に比べてエネルギーコストが高すぎるのではないかという意見は、現在でも見られる。このため、政府の産業競争力会議は成長戦略素案の中で「太陽光発電の発電コストを平成42年以降に7円/kWhまで引き下げる」と明確に打ち出した。すると、現行のFIT制度下での買い取り価格が引き下げられ、太陽光発電事業のうまみが薄れはしまいか。
これに関しては「グリッドパリティ(商業電力など既存の電力と発電コストが等しいか、それ以下になるポイント)に近づけない存在は、社会的に見て無駄だ。現在の再生可能エネルギー賦課金は、エンドユーザーの一般家庭などが支払っている。国内では42円/kWhという価格が打ち出され市場が盛り上がったが、今度はグリッドパリティを意識してエンドユーザーの負担をなくす方向に向かわなければならない。1兆円産業に成長したのだから、グリッドパリティを近づける力は既にあるはずだ」(阪本氏)とのことだ。
さらに、再生可能エネルギーは太陽光だけではない。単機出力が太陽光と比べ格段に大きな風力、発電のイニシャルコストが最も安価と見られる小水力、地域の間伐材対策などとして期待されている木質系バイオマス発電も再生可能エネルギーだ。これら他の形態の発電設備と送電線の競合や争奪戦が起こっている。この現状は「発電コストが下がれば、蓄電池の併用も大きなハードルではなくなってくる。規模の経済学が働いて、十分ペイするようになる。長い目で見れば、そう気にする必要もないのではないか」(阪本氏)と、市場展望は明るいようだ。そのために、再生可能エネルギーの先進地域である欧州の本社などから、主力となる製品や技術・情報面の情報とフィードバックが得られるのは大きな利点だ。国内市場で常に先手を打ち続けてきたABBが今以上に存在感を示せるか、今後に注目したい。